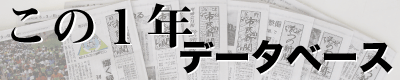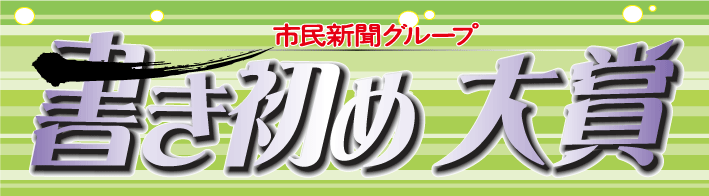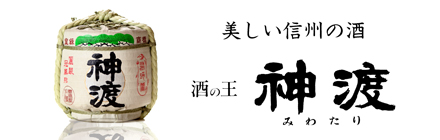NEWS
旧家に伝わる明治〜昭和の着物 岡谷蚕糸博物館で公開
2025年10月13日
岡谷蚕糸博物館で、東御市の竹内家から昨年度に寄贈された明治から昭和にかけての着物などを初公開する企画展が開かれている。祝い着や晴れ着、家庭内で作られた日常使いの着物など60点を展示。蚕糸業が発展した信州の旧家に伝わる着物文化を発信している。11月16日(日)まで。
寄贈者は、JA長野中央会南信支所長として上伊那、下伊那地域にあった組合製糸の操業停止に立ち会ったという竹内春彦さん(85)。曽祖父から父の代までは蚕種業を営んでいたという。同館が2023年に開いた企画展で、製糸業に関わっていた家庭などの絹衣装を紹介したのを見て、帯や小物類を含む約200点を寄せた。
展示するのは、竹内さんの家族や親族が着た品々という。子ども用は、魔よけの「背守り」が施された七五三の祝い着などが並ぶ。女性の着物は鮮やかな色彩や大胆な文様が特徴で、同館は「戦争の重い空気がない大正から昭和初期の華やかな様子が感じられる」とする。
売り物にならない繭から取った糸で仕立てた「うち織り」の着物や、羽織の裏地や靴下などをほぐして使った裂き織りのこたつ掛けなど、家庭内の手仕事で生まれた品もある。蚕種業を営んでいた時、竹内さんの曽祖父が販売先を訪ねる際に着用したという腹掛け、ももひき、羽織や蚕種販売帳、携帯そろばんなどの道具も紹介する。
同館学芸員の原田留津子さんは「豪華で華やかな着物から手間、愛情がこもった手仕事のうち織り、裂き織りなどから幅広い絹の魅力を感じてほしい」と話す。
午前9時〜午後5時。水曜と祝日の翌日は休館。入館料は530円(中高生320円、小学生170円)。問い合わせは同館(電0266・23・3489)へ。
(写真は、明治から昭和にかけての着物を紹介する会場)

 トップ
トップ ニュース
ニュース 新聞案内
新聞案内 各種案内
各種案内 会社情報
会社情報 お問合せ
お問合せ