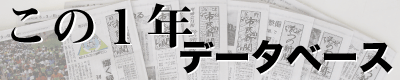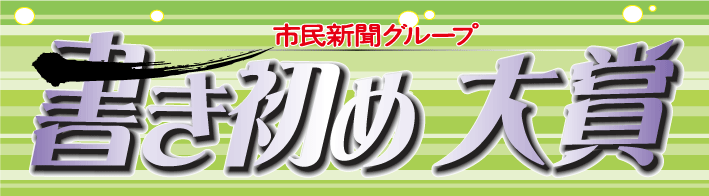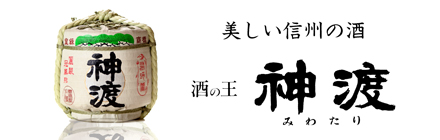NEWS
「ざざ虫漁」文化財指定を 伊那市の審議委が答申
2025年9月30日
伊那谷の冬の風物詩「ざざ虫漁」について、伊那市の文化財審議委員会は29日、市指定無形民俗文化財(民俗技術)にするよう、福與雅寿教育長に答申した。指定されれば、無形民俗文化財としては9件目、民俗技術としては初となる。
ざざ虫はカワゲラ、トビゲラ、ヘビトンボといった水生昆虫の幼虫の総称。漁は「虫踏み」ともいわれ、川底の石をくわでひっくり返したり、金属製のかんじきでかいたりして流れた幼虫を小型の四つ手網で受ける。現在は天竜川漁業協同組合(同市)管内の天竜川と支流でのみ行われている。
市教委の調査報告書によると、水生昆虫を対象とした漁は例が少なく、上伊那地域では1894(明治27)年の文献に食用にしていた記述がある。かつて県内の他地域でも漁は行われていたが、四つ手網を使った漁法は上伊那特有で、漁具もほとんどが手作り。採った虫は市内の業者が買い取り、つくだ煮などにして販売するなど地場産業として確立している。
北原紀孝委員長は「風土と生活と結び付いて育まれたざざ虫漁は、市の地域的特色を示す重要な文化財」と答申書を提出。受け取った福與教育長は「市教育委員会に諮り、文化財指定に向けて進めていきたい」と応じた。指定の可否は市教育委員会10月定例会で決める。
ざざ虫漁は、漁師の減少が最大の課題。1990年代には70人以上いた従事者は、近年は10人ほどにまで減っている。北原委員長は「子どもたちが地元の文化を見直す一歩になれば」と期待する。
文化財指定をめぐっては、市教委側は当初「ざざ虫漁とその食習慣」として諮問。7月の審議会では「食習慣というほど確立しているのか」などの慎重論が相次ぎ、継続審議となっていた。今回は漁のみを指定し、食習慣については今後も調査などを重ねる。
(写真は、ざざ虫漁の様子=2024年12月1日)

 トップ
トップ ニュース
ニュース 新聞案内
新聞案内 各種案内
各種案内 会社情報
会社情報 お問合せ
お問合せ