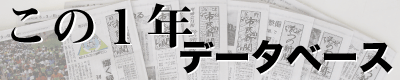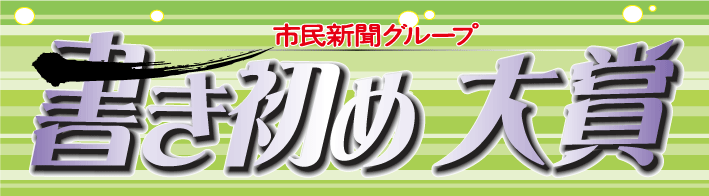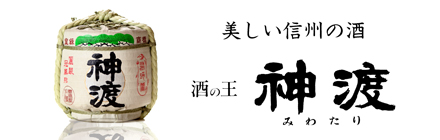NEWS
無病息災願いお舟巡行 箕輪町南小河内区で民俗行事「おさんやり」
2025年8月17日
南小河内区で16日、区内に200年以上伝わるとされる盆の民俗行事「おさんやり」(町無形文化財)が行われた。白装束の男衆約30人が、全長約9メートル、高さ約4メートル、重さ約400キロの「お舟」を巡行。区内の安全や区民の健康を願った。
天竜川と逆の方向に流れる区内の用水路「大堰(おおせぎ)」を介して疫病が流行したのを機に、無病息災を願って始まったとされる行事。災いを集め、外に追いやる役目のお舟を担いで回り、帰着後に壊す。木っ端は一年間の厄よけとして、住民が持ち帰る。
現在は、区役員らでつくる盆祭実行委員会が中心になって継承。お舟は13日、本体をカラマツ、船首と船尾はナラの材で組み立て、ササを縄で巻き付けて装飾。台車が付いた子ども用の「ミニお舟」もこしらえた。
2020年から巡行ルートが短縮され、ことしはやや延ばして約1.3キロの道のり。ルートの半分はキャスターによる巡行で、途中のつじでは「よいそれ節」などを披露。最後の100メートルほどはキャスターを外して担ぎ、1時間半ほどかけて堂の前に戻った。総合の学習でおさんやりについて学んでいる箕輪東小学校の4年生もミニお舟を先導で引っ張った。
式典や盆踊りをした後、お舟は立てたナラの木を3周して倒された。担ぎ手が枠に乗り、周囲が力強く揺すって破壊。区民が木っ端を選んでお守りにした。実行委員会会長の倉田昌区長(68)は「区民の皆さんの協力を受け、歴史と伝統がある行事が盛大にできて良かった」と話していた。
(写真は、白装束の男衆によって区内を巡行するおさんやりの「お舟」)

 トップ
トップ ニュース
ニュース 新聞案内
新聞案内 各種案内
各種案内 会社情報
会社情報 お問合せ
お問合せ