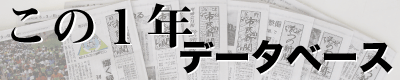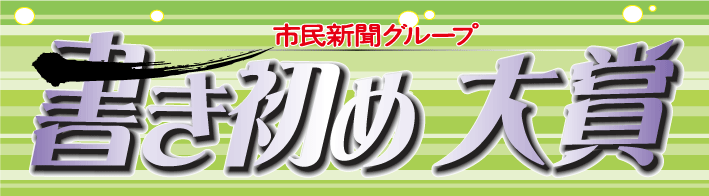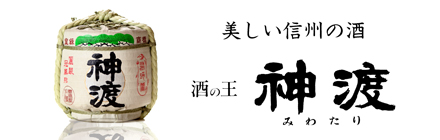NEWS
辰野町胃集団検診50年の歩み 記念誌に
2025年4月8日
辰野町の胃集団検診(胃集検)が2024年に50周年を迎えたことを受け、町が歴史や実績をまとめた記念誌を作った。治せる早期胃がんの発見を目的に1974年に始まり、検診車を使って50年間で延べ6万7619人を診察。102件の胃がんを見つけ、全国的にも高い精度を誇る。胃集検を始める提案をし、現在も携わる辰野病院非常勤内科医の松﨑廉医師(82)は「半世紀続き、感無量の思い」とページをめくり、歩みを振り返っている。
町の胃集検には、バリウムを用いた間接X線撮影と、検査画像を読み解いて診断する読影が必要。まだ撮影技術や読影知識が普及していなかった時代、町は撮影用の中古検診車を導入して始め、各地区を巡回する方式で実施。撮影は同院の放射線技師が担い、2002年からは県健康づくり事業団に委託する。読影については町内開業医と同院医師が携わっている。
胃がんの発見率は50年間で0.15%と、全国平均の0.1%を上回っている。見つかった胃がん102件のうち56件が早期胃がんで、「助かりやすいがん」を多く発見してきた。読影後の精密検査の受診率も50年間で92.9%と高い数値を残している。
同院院長も務めた松﨑医師は町の胃集検の「生き証人」。1972年、同院からいったん離れ、東京都内のがん検診センターで1年ほど最新の胃集検について学んだ。同院に戻ってくると、得たノウハウを生かして地域の健康を守りたい—と実施に向けて奔走。町医師会に協力を打診し、中古検診車の確保に尽力した。
一例でも多く早期がんを見つけようと、医師の読影力の強化にも力を入れた。読影後に症例検討会を開催し、医師が意見を言い合える場をつくった。当時、同院と医師会は今ほどつながりが強くなかったというが、「検討会を通じて信頼が生まれた。これは胃集検がもたらした副次的効果」と話す。
松﨑医師は「医師、放射線技師、保健師をはじめとする行政の人の努力や協力があって続けられた」と感謝する。今後の胃集検はバリウム検査よりも内視鏡を用いた検査が主流となりそうだが、「内視鏡が嫌でバリウムの方がいいという人もいると思うため、これからも続けていければ」としている。
記念誌はA4判、63㌻。100部を作り、関係者に配った。1991年に始まった大腸集団検診についても掲載。33年間で7万5369人を診察し、149件の大腸がん、88件の早期大腸がんを発見したことを伝える。
(写真は、町の胃集団検診50周年の記念誌を手に取る松﨑医師)

 トップ
トップ ニュース
ニュース 新聞案内
新聞案内 各種案内
各種案内 会社情報
会社情報 お問合せ
お問合せ