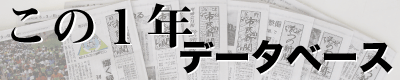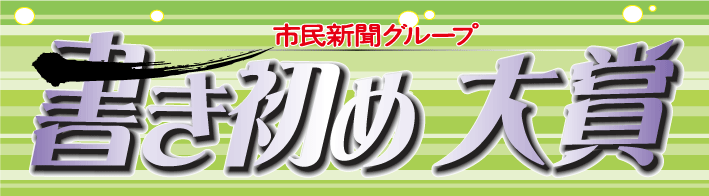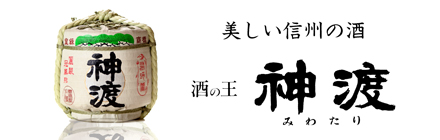NEWS
次回御柱祭の元綱用に 下諏訪町「四王藁の会」が稲わらの刈り取り
2025年9月29日
2028(令和10)年の諏訪大社下社御柱祭に向け、下諏訪町四王地区の有志でつくる「四王藁(わら)の会」は28日、秋宮一の元綱の材料となる稲わらの刈り取り作業を行った。御柱の曳き綱をわらから作っているのは現在、上社下社を通じて同地区だけ。地域の子どもたちも参加し、作業を伝承した。
稲わらを栽培している西四王の田んぼ(約700平方メートル)に会員10人と、園児から小学6年生まで15人が集合。子どもたちは地区PTAと育成会の指導で、田んぼの一角にことし5月、手植えした稲を、鎌を使って刈り取った。会員たちは稲刈り機で収穫し、子どもたちが刈り取った稲と一緒にはぜかけ。2週間ほど乾燥させてから脱穀し、わらは田んぼ横の倉庫で保管する。
一般的な稲より丈が長い「関取」という品種を栽培しているが、ことしは猛暑の後押しもあって例年以上にできが良く、1.5メートルほどの長さに成長。おんばしらの前年27年までの3年間で、前回より千束多い約3千束を調達する計画だが、出足は上々という。
芦部健二会長(63)=南四王=は「綱打ちの練習に使ったり、希望者に奉納する綱の分を含めて多めに用意する。いろいろな人に心配していただいたが、天気が良くて思っていた以上に育ってくれた。大勢の人と無事に収穫できて良かった」とうれしそうな表情を浮かべていた。
同地区は1950年から、第三区の依頼で山出しで使う秋一元綱女綱(進行方向左側)の綱打ちを担当。かつては地区内から提供されたわらを使っていたが、農家の減少や品種改良で丈の短いわらが主流となったことなどから、09年に有志で藁の会を結成。地区内に専用田を設け、関取の栽培を始めた。
伝統や文化継承のため、PTAや育成会の協力で子どもたちにも作業に加わってもらっており、田んぼには稲刈りに励む子どもたちや見守る保護者らの声が響いた。参加した児童(9)は「ざくざく切れて、気持ち良かった」と笑顔だった。
(写真は、元綱となる稲わらを鎌で刈り取る子どもたち)

 トップ
トップ ニュース
ニュース 新聞案内
新聞案内 各種案内
各種案内 会社情報
会社情報 お問合せ
お問合せ