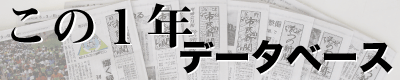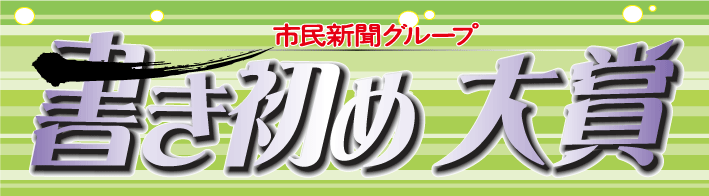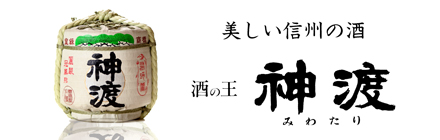NEWS
「藩譜私集」欠落の第7巻翻刻 博物館友の会員2人が尽力
2025年5月7日
高島藩研究のバイブル的存在「藩譜私集」(全23巻)のうち、欠落していた第7巻が諏訪市博物館収蔵資料から9年前に見つかった。これを博物館友古文書学習会員2人が解読と翻刻を行った後、家系図や考察などを交えてまとめ、失われたと思われたピースが3月末発刊の「諏訪市博物館研究紀要7」で発表された。
「藩譜私集」は高島藩士の鵜飼傳右衛門盈進(1815〜84年)が江戸から明治にかけ、同藩士200余家の家譜を著した23巻。家老から徒士までの幼名、通称、辞官名をはじめ、生没年、母系までも含めその一代の経歴が記され、藩諸家の系譜を知る上で欠かせない文献とされる。
その後、大正から昭和中期にかけて刊行された「諏訪史料叢書(そうしょ)」(全38巻、同叢書刊行委員会発行)のうち22〜24巻で藩譜が掲載された。しかし、編さん当時には2巻と7巻は目次のみの記載にとどまり、行方知れずになっていた。
市博物館は所蔵の鵜飼家資料を調査する中で、2016年に第7巻を発見。これを受けて、友の会古文書学習会の原寿樹代表(57)と田中生浦さんが名乗りを挙げ、同年から1年がかりで解読、翻刻。その後は記載される各人物像の調査を進めた。紀要には鵜飼家の出自、戦国時代から近世までの動きなどと共に、系図を掲載する。
2人は「欠番があるのは悔しかった。何とか世に出せたことがうれしい」と口をそろえる。原さんは「第3代藩主の忠晴が鵜飼家で生まれたことや、上社神宮寺五重塔にあった五智如来が京都から勧請(かんじょう)したことなど小さな発見もあった」と喜びを感じ、田中さんも「著者である鵜飼家を記した第7巻が、館所蔵史料から見つかったのも何かの縁。第2巻が見つかったら、ぜひ、解読、翻刻したい」と話す。
三嶋祥子学芸員は「高島藩を研究する上では私集は欠かせない存在。失われた思っていた一部が見つかったことは、大きな意義がある」とする。
紀要の発刊は11年ぶり。旧御射山遺跡出土物の再検討、寄託・諏訪上社大工棟梁(とうりょう)原家資料についてのまとめもある。A4判、128ページ。1200円(税込み)で頒布する。
問い合わせは同館(電0266・52・7080)へ。
(写真は、解読、翻刻した原さん㊨と田中さん)

 トップ
トップ ニュース
ニュース 新聞案内
新聞案内 各種案内
各種案内 会社情報
会社情報 お問合せ
お問合せ